創造力は子どもの将来を左右する?定義や必要な理由、創造力を養う方法を徹底解説!
サイト運営会社
株式会社城南進学研究社
「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん/アタマGYM」「りんご塾」 「Zoo-phonics Academy」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、 「城南進研グループ」を形成。

子どもの将来は生まれ持った資質に加え、環境を含むさまざまな要因で大きく変わります。子どもの将来に大きな影響を与える要素の1つに創造力がありますが、そう聞いても「創造力とは具体的にどんなものがわからない」「創造力を養う方法がわからない」と不安に思う方も多いでしょう。
そこで本記事では、創造力の定義や創造力が子どもに必要な理由、創造力を高める方法を詳しく解説します。
現在育児中の方や創造力について興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
創造力とは?その意味と必要な理由

そもそも創造力とはどのようなものなのでしょうか?想像力との違いがわからない、と考える方も多いでしょう。
そこでこの章では、創造力の定義や必要な理由について解説します。
創造力の定義とは
一般的には、創造力とは「新しいものを自力で作り出す力」とされています。さらに、経済産業省が提唱する社会人基礎力※では、創造力は「新しい価値を生み出す力」と定義されています。
創造力とよく似た言葉に「想像力」があり、同じような使われ方をすることがありますが、違う概念です。
この2つの言葉はどちらも新しいものを生み出す力のことですが、想像力が頭の中で思いつく力に対して、創造力は思いついたものを実際に形にする力のことを指します。
例えば、物語を頭の中で考える力は想像力で、考えたものを物語として書いたり絵にしたりする力が創造力です。
創造力が必要な理由
現代ではAIの急速な発展により、機械でできる仕事が増えています。また、グローバリゼーション(国や地域などの枠を超えて資本や労働力が移動し、経済や社会、文化が地球規模で結びつくこと)やDX化(ITの浸透により生活の利便性を高めること)などにより、今まで通用していた常識や知識が通用しない予測不可能な時代を迎えようとしています。
このような社会を生き抜いていくためには、自分で新しいことを考え出し実行していく力、すなわち創造力が必要です。
創造力は脳の発達により引き出されると考えられているため、脳がもっとも発達する幼少期に適切な刺激を与えると、より高めることができます。
子どもの創造力を高める方法

創造力の重要性は理解したものの、どうやったら子どもの創造力を高めることができるのだろうか?と思う方は多いでしょう。
子どもの創造力を高めるためには、以下の8つのポイントを押さえることが大切です。
・自由に遊ぶことができる時間を与える
・自由に遊ぶことができる場所を与える
・子どもが工夫して遊ぶことができるものを与える
・大人が創造する姿を見せる
・大人が何でも先回りしない
・子どものアイデアを聞く
・褒め方や感想の伝え方に気をつける
・「失敗してもOK」の心構えでいる
自由に遊ぶことができる時間を与える
遊びは、子どもが持つ可能性を高めるために大変重要です。遊びを通して創造力を高めるためには、ルールやスケジュールなどに縛られずに自由に遊ぶ時間を与えましょう。
親に頼ることなく一人で思うように遊ぶと、自分だけの遊びを生み出したり楽しみ方を見いだしたりして創造力を養うことができます。
子どもが夢中になって遊びだしたら、危険なことがない限りは口出しせずに見守ることも大切です。
自由に遊ぶことができる場所を与える
子どもが自由に遊び創造力を養うためには、安心して自由に遊ぶことができる場所も必要です。
体を動かす、絵の具や粘土などを使用する、おもちゃを好きなだけ使用する、などの行為はある程度の空間がないとできません。
安心して遊べる広い公園や広場、遊び場を確保しましょう。自宅で用意する場合は、できるだけ広い空間がある部屋を用意し、家具の角などのけがの危険があるところはカバーを掛けましょう。
子どもが工夫して遊ぶことができるものを与える
子どもが自由に遊ぶためには、おもちゃや道具が必要です。使い方が決まっているものではなく、工夫次第でさまざまな遊び方ができるものを用意するとよいでしょう。
創造力を高めるためにはできるだけシンプルなものがよく、外遊びなら砂場、室内ならブロックや積み木、粘土、紙やはさみ、のりなどの工作グッズがおすすめです。
空き箱やトイレットペーパー、ラップ類の芯などの素材も、創造力を高める効果が期待できます。
大人が創造する姿を見せる
子どもは、親をはじめとする大人のやることを見て育ちます。新しいものを創造する行為は口で説明してもピンとくるものではありません。
親が楽しんで創造する姿を見ると、子どももお手本にします。楽器や歌、絵画、料理、ガーデニング、などはすべて創造力を養う効果があります。
また、日常生活の中で困ったことが起こった時に、親が率先して解決のためのさまざまな方法を考えて実行することもよいお手本になるでしょう。
大人が何でも先回りしない
新しいことにチャレンジすると、失敗も多く起こります。子どもを見守っていると、ついハラハラして「そうするとだめだよ」「こうした方がいいよ」と口出しをしてしまいがちです。
しかし、口出しや先回りなどの行為は、子どもに失敗を恐れる気持ちを植え付けたり、自立心を損ねたりする危険性があります。
子どもが遊んでいる時は口出しせずに見守り、子どもが助けを求めてきたら「どうしたらいいと思う?」と声掛けするとよいでしょう。
子どものアイデアを聞く
子どもに助けを求められたり質問されたりした場合は、答えのみをすぐに教えるのではなく、子どもにも考えさせることが大切です。
自分のアイデアを尊重されると子どもは自信がつき、次からもアイデアを考えようとするでしょう。
子どもと一緒にどうすればよいのかを考えて解決に向けて試行錯誤することは、創造力を高めることへと繋がります。
褒め方や感想の伝え方に気をつける
子どものアイデアを褒めたり感想を伝えたりする際には、褒め方や伝え方に気をつけましょう。
結果よりも結果に至るまでのプロセスや工夫、努力を褒めてください。「すごいね」「よくできたね」ではなく、「この工夫がよいね!」「いろいろな色を使っていて素敵だね」など、具体的に褒めたり感想を伝えたりしましょう。
そうすると、子どもにより伝わりやすくなり、さらなる創造力の向上へと繋がります。
「失敗してもOK」の心構えでいる
新しいことを生み出す際には、失敗はつきものです。失敗したからと言って落ち込んだり否定したりすると、新しいことにチャレンジすることを恐れるようになってしまいます。
失敗しても、「では次からどうすればよいだろうか?」と考えることが創造力を鍛えます。失敗をネガティブに捉えるのではなく、成功へのプロセスだとポジティブに捉えることが大切です。
もしも子どもが失敗して落ち込んでいたら、「次はどうしたらいいのか一緒に考えよう!」「どこが失敗の原因だったと思う?どうしたら改善できるだろうか?」など、一緒に考えてあげましょう。
子どもの創造力を鍛える具体的な方法

この章では、創造力を高める効果が期待できる具体的な方法を紹介します。上記で解説した子どもの創造力を高めるための8つのポイントを押さえながら行うと、より高い効果が期待できます。
また、創造力を高める効果が期待できる教室も紹介しているので、興味がある方はリンク先からホームページをご覧ください。
・ごっこ遊び
・工作・何かを作る遊び
・リトミック・ダンス
・プログラミング
ごっこ遊び
ごっこ遊びは自分ではない人になりきり、そのシチュエーションにあった発言や行為を行うため、創造力を必要とする遊びです。
年齢や性別を問わずにでき、場所もあまり必要としないため、家庭でできる創造力を高める遊びとして適しています。
さまざまなキャラクターや状況を考えることは、自分以外の視点や考え方、感情を理解する力を向上させ、創造力の向上に大変役立ちます。
工作・何かを作る遊び
粘土やブロック、砂場で何かを作る作業は、創造力を働かせます。はさみやのりを使うことができるようになったら、工作も創造力を高める効果が大変期待できる遊びです。
はさみやのり、段ボールなどのシンプルな素材を前にして「何を作ろうか」「どのようにしたらもっとよくなるだろうか」と考えて試行錯誤を繰り返すと創造力が高まります。
また、筆、クレヨン、指、身体などあらゆる道具を用いて絵を描くことも想像力を鍛えます。
アトリエ太陽の子は、「上手」「下手」などの評価ではなく、自由に自分を表現することで創造力を伸ばすことができる教室です。
段ボールから立体作品を作ったり、大きな紙にフィンガーペインティングで自由に絵を描いたりしながら楽しく創造力を養うことができます。
リトミック・ダンス
創造力は、五感を使うことでも増します。聴覚を使うリトミック(音楽に合わせて自由に体を動かすことでリズム感や音感などを養う遊び)やダンスは、耳で聞いた音楽のイメージを体で表現しようとする際に創造力を必要とします。
すぐには体で音のイメージを表現できない場合は、特定の体の部位を動かしたり、音の高低を動物の動作で表すようにアドバイスしたりすると取り組みやすくなるでしょう。
プログラミング
コンピューターを使うことと創造力はあまり関係がないように思われるかもしれませんが、コンピューターに指示を出してさまざまな動きをさせるようにする作業は、どのようにプログラミングをすればよいのか試行錯誤を繰り返すため、創造力が養われます。
プログラミング教育は2020年より小学校から導入されていますが、プログラミング教室に通うことでより創造力を高める効果が期待できます。
キッズブレインパークのプログラミング教室Viscuit(ビスケット)は、ビジュアルプログラミング言語「Viscuit(ビスケット)」を活用したプログラミング教室です。
アート性が高く、ビスケットで描いた絵を自由に動かしたり自分の考えや感情を表現したりできるため、単なるプログラミング的思考のみではなく、表現としてのプログラミングが身につき、創造力も養うことができます。
まとめ
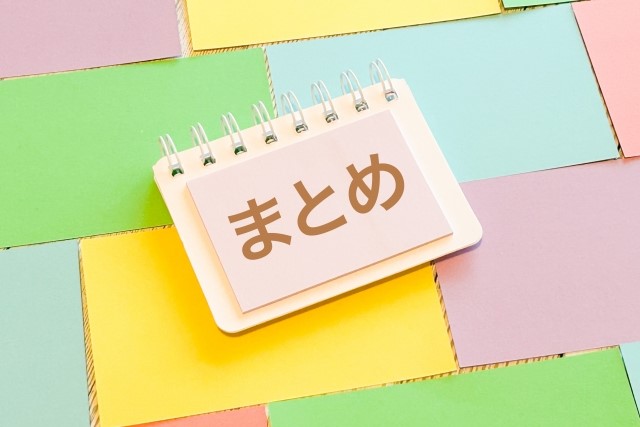 創造力は、これからの社会を生き抜いていくために必要な力です。大人になってからでも育むことができますが、幼児期に特に成長するため、この時期に適切な対応をすると可能性を最大限に引き出すことができるでしょう。
創造力は、これからの社会を生き抜いていくために必要な力です。大人になってからでも育むことができますが、幼児期に特に成長するため、この時期に適切な対応をすると可能性を最大限に引き出すことができるでしょう。
創造力を高めるためには難しいことは必要ありませんが、日常生活の中で意識した対応を心がけるとより効果的に養うことができます。創造力を高める効果がある遊びを取り入れたり、この記事で紹介した創造力を高めるためのポイントを実践したりすることをおすすめします。
児童教育の複合型スクールのキッズブレインパークには、創造力を高める効果が期待できる教室があります。
興味がある方は、ぜひホームページをご覧ください。
アトリエ太陽の子(3歳~小学生向け)
自由に自分を表現させ、一人ひとりの想像力を大切にして個性を伸ばします。
Viscuit(ビスケット)(年中~小学生向け) 楽しみながらアート性の高いプログラミングを身につけることができます。
キッズティンカリング(年中~小学生向け) 科学とアートを融合させ、試行錯誤を繰り返しながら新しいものを作り出します。
興味がある方は、ぜひホームページをご覧ください。
| アトリエ太陽の子(3歳~小学生向け) | 自由に自分を表現させ、一人ひとりの想像力を大切にして個性を伸ばします。 |
| Viscuit(ビスケット)(年中~小学生向け) | 楽しみながらアート性の高いプログラミングを身につけることができます。 |
| キッズティンカリング(年中~小学生向け) | 科学とアートを融合させ、試行錯誤を繰り返しながら新しいものを作り出します。 |


