0歳児への話しかけには意味がある!0歳児の言葉の発達や効果がある話しかけ方を徹底解説!
サイト運営会社
株式会社城南進学研究社
「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん/アタマGYM」「りんご塾」 「Zoo-phonics Academy」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、 「城南進研グループ」を形成。

赤ちゃんへの話しかけは、言葉や脳の発達、社会性の発達、学習能力の向上などに効果がある、と言われています。
しかし、「言葉が通じない相手に話しかけるのは恥ずかしい」「本当に効果があるの?」と疑問に思うパパ・ママも多いでしょう。
そこで本記事では、赤ちゃんに話しかけることの意義や、月齢別の話しかけ方、効果がある話し方や内容などについて詳しく解説します。
0歳児のパパ・ママや、0歳児に対する話しかけについて興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
1. 赤ちゃんに話しかけることの意義

赤ちゃんに話しかけても明確な返事は返ってこず、「だめ」や「いいよ」などの言葉も通じません。そのため、「本当に話しかけに効果があるのだろうか?」と疑問に思う方もおられるでしょう。
この章では、赤ちゃんに話しかけることの意義について解説します。
言葉の発達は生まれた瞬間から始まる
生まれたばかりの赤ちゃんは、言葉を発することも理解することもできません。しかし、音は聞こえており、言葉の意味は理解できなくても音や声のリズムなどを聞き分けて、言葉の学習を開始しています。
赤ちゃんの脳の神経回路は生まれた時にはつながっておらず、刺激を受けることでつながります。生後の早い段階から積極的に話しかけると脳に刺激を与え、言葉や知能の発達を促すため、赤ちゃんへの話しかけは重要です。
親子の絆を深めるコミュニケーション
赤ちゃんは、お腹の中にいる時からママの声を聞いているため、ママの優しい声を聞くと、安心してリラックスします。
泣いたり笑ったりすることで「気持ちが悪い」「心地よい」などの気持ちを伝え、月齢が進むにつれてクーイング(喃語の前の段階で「あー」「うー」などの単語を発する)や喃語を発するようになります。
それに対して、パパやママが「お腹がすいたのかな?」「おむつが濡れて気持ち悪いね」などの声かけをすると、赤ちゃんは自分の気持ちが伝わったと感じ、親子の絆が深まっていきます。
脳の発達を促進し、知能の基礎を築く
上記でも解説しましたが、脳の神経回路は刺激を与えることでつながります。そのため、パパやママが積極的に話しかけると、言語能力を司る神経回路がつながり、語彙力や知能指数の発達を促します。
また、情緒の安定や社会性、思考力などにもよい影響を与え、さらには身体機能の成長やコミュニケーション能力の育成にも効果が期待できるでしょう。
2. 赤ちゃんはいつから大人の言葉を理解するのか?

生まれたばかりの赤ちゃんは大人の言葉を理解できませんが、成長するにつれて徐々に理解していきます。
赤ちゃんの成長は著しいため、この章では、赤ちゃんの言葉に対する発達を月齢別に以下の3つの時期に分けて解説します。
・生後0〜2ヶ月:音に反応する時期
・生後3~6ヶ月:声を出し始める時期
・生後7〜12ヶ月:言葉の意味を理解し始める時期
生後0〜2ヶ月:音に反応する時期
生まれてすぐの赤ちゃんの視力は0.01〜0.02程度と低く、あまり見えていませんが、音はしっかりと聞こえています。
口や鼻の中の声を出す部分が未発達のため話すことはできませんが、ママの声や、人間と人間でないものの音を聞き分けることができ、声がする方向を向いたり手足をバタバタを動かしたりします。
生後3~6ヶ月:声を出し始める時期
生後3ヶ月を過ぎるとクーイングが始まり、4ヶ月を過ぎると「あーうー」「あーあー」などの喃語を発するようになります。
いろいろな音の高さや長さの音を出して音声を試すようになり、5ヶ月頃には、「なんなん」「まんまん」など、子音を含む喃語を発します。
この頃になると、パパやママの話しかけに声を出して答えるなど、声を使ったコミュニケーションが可能になるでしょう。
生後7〜12ヶ月:言葉の意味を理解し始める時期
この頃になると、左脳にある言葉の理解や表現を司る言語野の活動が活発になり、言葉の意味を理解し始めます。
「ブーブー」「まんま」などの意味がある喃語を発するようになったり、「ママ」「パパ」「バイバイ」などのよく聞く言葉に反応したりするようになります。
話しかけに対して反応を示すことを繰り返していく過程で言葉を徐々に覚え、意味がある言葉を発する準備が整っていきます。
3. 月齢別に見る赤ちゃんへの話しかけ方

0歳児に話しかけることの重要さは理解したものの「具体的にはどのような話しをしたらよいのかわからない」と悩むパパ・ママも多いでしょう。
0歳児は成長が著しいため、より効果的に言葉の発達を促すためには、成長に合わせた話しかけを行う必要があります。
この章では、月齢別に赤ちゃんへの話しかけ方を解説します。
0~2ヶ月の赤ちゃんへの話しかけ方
この時期はほぼ寝たきりで、視力も低いですが音は聞こえている状態です。
話しかける時は、はじめに赤ちゃんの目を見て赤ちゃんの意識をママに向けたのち、口を大きく開けて聞き取りやすいように、ゆっくりと優しい声で話しかけましょう。
また、抱っこやタッチなどのスキンシップをまじえて、「おはよう」「どうしたの?」「気持ちいい?」など、シンプルな言葉をかけるとよいでしょう。
3~6ヶ月の赤ちゃんへの話しかけ方
音に対する反応が少しずつ鋭くなり、パパやママの声に対する反応もよくなってきます。言葉の発達やコミュニケーション能力の基礎をつくる時期なので、どんどん話しかけましょう。
クーイングや喃語を発した時には、赤ちゃんをまねて「あー」「クー」と声をかけたり、「気持ちいい?」「楽しい?」「どうしたのかな?」など返事をしたりするとよいでしょう。
7~12ヶ月の赤ちゃんへの話しかけ方
発音や発声が上手になり、音と動作が結びつくようになります。大人のまねをして「バイバイ」や「パチパチ」などができるようになるため、動作をつけて話しかけるとよいでしょう。
学習能力も高くなっており、「ワンワンがいるよ」「これは○○だね」などの短い文章で名前を教えたり、赤ちゃんの指さしに答えたりするとより言葉を理解できます。
また、食事をさせる時には「おいしいね」、外出する時には「出かけようね」など、行動と話しかけの内容を一致させると、赤ちゃんが学習しやすくなるでしょう。
4. 赤ちゃんに話しかける内容に迷ったら

赤ちゃんへの話しかけは、日常的に行うことが重要です。
しかし、赤ちゃんに話しかけようと思っても、「おはよう」「ごはんだよ」などの簡単な声かけはできても、それ以上話すことが思いつかずストレスを感じる場合もあるでしょう。
その場合には、以下の3つの方法で話すとストレスにならずに、自然に話しかけをすることができます。
・日常の出来事を実況中継する
・絵本の読み聞かせを通じて話しかける
・「くぼた式育児法」の考案者である久保田カヨ子さんの言葉を参考にする
日常の出来事を実況中継する
基本的な挨拶や簡単な言葉かけが終わって「話すことがなくなった」と感じたら、日常の出来事をそのまま実況中継すると、自然に話しかけをすることができます。
おっぱいを飲んでいたら「ごくごく飲んでるね、おいしいね、お腹いっぱいになったかな?」散歩に出かけたら「風が気持ちいいね。お日様がニコニコしてあったかいね。あ、猫が歩いてるよ」など、目にしたものをそのまま口に出すだけです。
このような話しかけの繰り返しで、赤ちゃんは言葉と動作を結びつけて理解するようになります。
絵本の読み聞かせを通じて話しかける
絵本の読み聞かせも効果がある方法です。
0歳児向けの絵本はカラフルで短い文章で書かれており、擬音語(音や動物、人の声などを模した言葉:にゃーにゃー、ちゅんちゅんなど)や擬態語(状態や身振りなどを表した言葉:ニコニコ・ふわふわなど)が多く使われています。
これらの言葉は赤ちゃんが聞き取りやすいため、言葉の学習の手助けとなるでしょう。さらに、読み聞かせながら「このワンワン、楽しそうだね」「おいしそうなりんごだね」などの話しかけをすると、自然に会話を続けることができます。
図書館や絵本のサブスクリプションを利用すると、負担にならずに多くの本に触れることができるため、おすすめです。
「くぼた式育児法」の考案者である久保田カヨ子さんの言葉を参考にする
久保田カヨ子さんは、世界的な権威の脳科学博士である久保田競先生を夫に持ち、その育脳理論を自分自身の子育てで実践した方です。
のちに競先生とともに「頭のいい子を育てる育児法」を考案し、「子どもの脳は5歳までで決まる!」と説いて、「1歳前後にたくさんの刺激を与えることが重要」と述べています。
久保田カヨ子さんの提唱する育児法の一つに、「おむつを替える時には必ず声をかける」というものがあります。
おむつを替える時に「おむつを替えたら気持ちがよくなったね」と、気持ちがよくなった言葉を繰り返しかけると、赤ちゃんは声の調子や表情などからその言葉の意味を理解し、表情が豊かになる、というものです。
おむつ替えの時だけでなく、日常の動作でもこのような声かけを意識するとよいでしょう。
5. 赤ちゃん言葉を使わない理由
近年では、赤ちゃんには赤ちゃん言葉で話す方が発達を促す、との考え方が主流となりつつありますが、久保田式育児法では、赤ちゃん言葉は推奨されていません。
その理由には、以下の2つが挙げられます。
・正しい言葉の使用が成長によい影響を与える
・ロールモデルとしての親の役割を果たす
正しい言葉の使用が成長によい影響を与える
子どもの記憶力は素晴らしく、聞いた言葉をどんどん吸収します。赤ちゃん言葉を否定はしませんが、正しい言葉で話しかけると、そのままストレートに正しい言葉を覚えるため、無駄がありません。
生まれてすぐから、できるだけ簡単ではっきりした言葉で話すようにし、「りんご」と言った単語のみではなく、「このりんごは丸ごとかじることはできないから小さく切ろうね」など、「文章」で話すようにすると、より効果的に正しい言葉を覚えることができます。
ロールモデルとしての親の役割を果たす
赤ちゃんがさまざまなことを学ぶお手本はパパやママの言動で、その中でも一番最初にお手本にして覚えるのが言葉です。
正しい言葉もそうでない言葉もどんどん吸収していくため、お手本となるよう正しい言葉で話すことが望まれます。
実際に、親が子どもに正しい言語モデルを示すと、子どもの言語発達によい影響を与えることが、研究でも判明しています。
まねしやすいように、話しかける時には口元を見せてはっきりと発音し、とくに母音で始まる単語ははっきりとした発音を心がけ、よく使うとよいでしょう。
6. 賢くなるための言葉の環境づくり
言葉の発達は、パパ・ママの対応だけでなく、周囲の環境も影響します。適切な対応に適切な環境を整えることで、言葉の発達をより促すことができるでしょう。
この章では、賢くなるための言葉の環境づくりについて解説します。
環境が言葉の発達に与える影響
言葉は脳の発達に関係するため、心や脳に対する対応に目が行きがちです。しかし、脳に流れ込んでくるさまざまな刺激を適切に活用するためには、元気な身体や安心して過ごせる環境をつくることが重要だと考えられています。
0歳児は、パパ・ママをはじめとする養育者の模倣をすることで、言葉を理解していきます。そのため、日頃から正しい言葉を使い、コミュニケーションが密に行われている環境で育てることが豊かな言語習得につながります。
また、さまざまな体験ができる地域のイベントや、絵本を借りたり読み聞かせコーナーが利用できたりする図書館の利用も、言葉の発達によい影響を与えるでしょう。
家庭でできる言葉の刺激方法
子どもの興味を引き出す環境は、言葉の発達に影響を与えます。
例えば、目に見えるところにカラフルなモビールをつるしたり、絵本を手が届くところに置いたりすると、子どもの興味を引き出すことができます。
これまで解説してきたように、日常的に話しかけを行ったり、絵本を読み聞かせたりすることも重要です。
また、音やリズムをまねする遊びを行うと、声を出す楽しみを知ったり発語のきっかけとなったりします。動物の鳴き声のまねや、いないいないばあなどの遊びも効果的です。
7. 【まとめ】
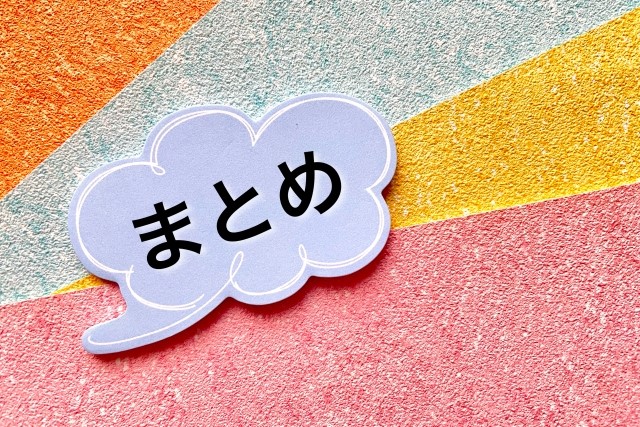
0歳児への話しかけは、言葉の発達を促すのみでなく、知能の発達を促したり親子の絆を深めたりするため重要です。
継続することが大切なため、この記事を参考に、毎日のあいさつや日常の出来事の実況中継、絵本の読み聞かせなどを、月齢に合わせて適切に行うとよいでしょう。
また、0歳児から通うことができる幼児教室に通うのも、赤ちゃんへのよい刺激になります。
児童教育の複合型スクールのキッズブレインパークには、0歳から通える以下の幼児教室があります。興味がある方は、ぜひホームページをご覧ください。
| Kubotaのうけん(0~2歳児向け) | 週に1回通うだけでなく、親を対象に家庭での働きかけ方やポイントを月齢別にサポートします。 |
| すくすくweb(0~3歳児向け) | ・「Kubotaのうけん」が監修した、お子様の育脳に関する指示を明確にまとめあげたオンライン親子教室。 ・週に1度発達段階に合わせた動画に取り組むことで育脳を促進します。 |
| アタマGYM (3~6歳児向け) | 知識の詰め込みではなく考える力を育み、創意工夫する力やコミュニケーション能力を高めます。 |


