忙しくても大丈夫!家庭でできる赤ちゃん教育の具体的な方法を徹底解説
サイト運営会社
株式会社城南進学研究社
「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん/アタマGYM」「りんご塾」 「Zoo-phonics Academy」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、 「城南進研グループ」を形成。

赤ちゃんの脳は2〜3歳までに著しく発達します。そのため、この時期に脳によい刺激を与えると発達をサポートできます。
しかし、この時期は育児に最も手がかかる時期であるために、お仕事をされていても、されていなくとも幼児教室へ通う余裕がないと悩む方も多いでしょう。
そこで本記事では、家庭でできる赤ちゃん教育の具体的な方法や、遊びのアイデアを解説します。現在、育児中の方や出産予定の方、赤ちゃん教育に興味がある方はぜひ参考にしてください。
幼児教育を日常生活に取り入れる方法

「幼児教育」「赤ちゃん教育」と聞くと、教室に通わせる、専門家の指導を受ける、親も大変、難しそう、などのイメージを持つ方もおられるかもしれません。
しかし、幼児教育は日常生活に取り入れることで、お金や特別な教材がなくても赤ちゃんの成長を促すことができます。
忙しくてもほんの少しの工夫で赤ちゃんの可能性は広がります。この章では、日常生活でできる幼児教育の方法を3つ解説します。
・毎日のルーチンに教育的要素を組み込む
・遊びを通じて学ぶ時間を設ける
・普段の会話で言葉を増やす
毎日のルーチンに教育的要素を組み込む
最も簡単かつ効果的な方法は、食事・お風呂・着替えなど、毎日の生活習慣の中に教育的要素を組み込むことです。
これらのルーチンを行う際には、まずはじめに「○○ちゃん、お風呂に入ろうね」など、声かけ時に名前を呼び、漫然と行うのではなく、数や色などを都度伝えるとよいでしょう。
- 例
| 食事中 | にんじん、おいしい?今日の〇〇ちゃんのお洋服と同じ色だね。 |
| 入浴中 | 30数えたらあがろうね |
| 着替え中 | 今日の服は何と同じ色かな? |
また、おはようやおやすみの挨拶はコミュニケーション能力によい影響を与え、絵本の読み聞かせは、言語習得のサポートをしたり、創造力を養ったりする効果があります。家族間での挨拶や就寝前の読み聞かせを習慣化するとよいでしょう。
遊びを通じて学ぶ時間を設ける
赤ちゃんは、遊ぶことでさまざまなことを学びます。遊びによりさまざまな刺激を受けることで、生きていく上で必要な体力や運動能力、認知能力、創造力、自発力、社会性などの発達を促すことができます。
- 例
| 公園の遊具などで遊ぶ | 登る、立つ、座る、すべる、などの動きが身につく |
| 鬼ごっこ | 走る、歩く、避ける、くぐるなどの動きが身につく |
| パズル・工作・お絵かき | 学習能力、認知能力、創造力の育成をサポートする |
| ボードゲームやごっこ遊び・ルールがある遊び | コミュニケーション能力や社会性を育んだり、協力することの重要性を学んだりする |
また、外遊びや散歩などで自然の色や音、匂いに触れさせることも、幼児教育につながります。
「風が吹いて気持ちがいいね」「葉っぱが赤くなってきれいだね」「あれはなんの音だろうね?」などの声かけをすることで脳に刺激を与え、感性を豊かにしたり知的発達をサポートしたりします。
普段の会話で言葉を増やす
赤ちゃんは一日の大半を家庭で過ごします。そのため、普段から会話が多い家庭で過ごすと脳に与えられる刺激も増え、言語取得や知的発達をサポートする効果が期待できます。
赤ちゃんに話しかける時は、口を大きく開けて大人の言葉をゆっくり、はっきりと話すとよいでしょう。
実は赤ちゃんは記憶力がよく、聞いた言葉をそのまま覚えてしまいます。正しい言葉で話しかけていると、そのまま正しい言葉を覚えるため、話す時は意識して正しい言葉で話しかけることをオススメします。
話しかける際は、感情がこもった声かけや、オノマトペ(擬音語、擬声語、擬態語のこと)を意識すると、赤ちゃんが理解しやすくなるでしょう。
- 例
| 擬音語 | ・雨がザーザー降ってるね ・はさみでジョキジョキ切っちゃおう |
| 擬声語 | ・犬がワンワン吠えてるね ・カラスがカーカーと鳴いてるよ |
| 擬態語 | ・お星様がキラキラしてるね ・ぐっすり眠ったから機嫌がいいね |
赤ちゃんのペースに合わせることが大切

赤ちゃん教育で発達をサポートするコツは、赤ちゃんのペースに合わせることです。
赤ちゃんの発達は個人差が大きくあります。「○歳では○○ができるようになる」などの一般的な発達速度に当てはめて発達に合っていない教育を行うと、期待した効果が得られなかったり逆効果になったりする場合があります。
親の希望や欲求を優先するのではなく、以下の3つのポイントに気をつけて行うと、効果的な幼児教育を行うことができるでしょう。
・赤ちゃんの反応を観察する
・急がずに時間をかける
・興味を持ったことに焦点を当てる
赤ちゃんの反応を観察する
赤ちゃん教育で大切なポイントの1つは、「押し付け」ではなく、赤ちゃんの興味を「引き出す」姿勢です。
赤ちゃんは言葉を話すことができないため、「行った教育が向いているのか、効果的であるのかがわからない」と不安になることも多いでしょう。
赤ちゃんは、月齢が進むにつれて視力も発達し、興味があるものを目で追うようになったり、手を伸ばしたりするようになります。
赤ちゃん教育を行う際には、赤ちゃんの反応をよく観察し、笑顔のあるなし・視線・手の動きなどから興味を読み取りましょう。
急がずに時間をかける
2つめのポイントは、急がずに時間をかけることです。赤ちゃん教育は、行うとすぐに効果が出るものではなく、毎日コツコツと行うことで効果が得られます。
また、習得のスピードは個人差が大きいため、他の赤ちゃんと比べて焦ったり、イライラしたりしないよう気をつけましょう。
大人でも、学ぶことには失敗や飽きがつきものです。赤ちゃん教育も同様なので、失敗や飽きも学びの一部であることを理解して、じっくりと腰を据えて行いましょう。
興味を持ったことに焦点を当てる
3つめのポイントは、赤ちゃんが興味を持った分野を選ぶことです。
赤ちゃん教育にはさまざまな分野があるため、「どれを選べばよいのかわからない」と悩む方は少なくありません。日頃から赤ちゃんの様子をよく観察し、興味がありそうな分野に焦点を当てましょう。
例えば、電車が好きな子には乗り物図鑑や模型遊びを取り入れたり、おままごとで料理に興味を示す子には、料理体験をまねできるおもちゃ(おもちゃの包丁で切ることができるものなど)を与えたりするとよいでしょう。
また、興味を示した分野について、本やテレビ、インターネットなどを利用して情報を与えると、語彙や知識を広げることができます。
豊かな体験を提供すると効果的

さまざまな体験を提供すると、赤ちゃん教育に効果的が期待できます。家庭でも、いつも同じ刺激だけでなく、違った刺激を与える工夫をするとよいでしょう。
外出時には、いつもと違う環境で、家庭では会うことができない人やもの、風景、体験に触れると脳によい刺激を与えます。
家庭内での工夫
家庭では、以下のような工夫で、いつもと違う刺激を与えることができます。
- キッチンでの簡単な食材観察
キッチンは、赤ちゃんが普段生活している場所(リビングや子ども部屋など)にはないものが多くあります。
特に食材は、メニューにより扱うものが異なるため、毎回新しい刺激を与えることができます。食材を見ながら、色や形を観察したり、味について語りかけたりするとよいでしょう。
- 家族写真やアルバムを使った会話のきっかけづくり
家族写真やアルバムを見ると、会話がスムーズに発展します。いつもと違う会話を聞くことは、脳に刺激を与える効果があります。
また、研究※によると、赤ちゃんは生後12ヶ月くらいから自分の顔を認知できることが判明しています。12ヶ月を過ぎた赤ちゃんに家族写真やアルバムを見せると、自己認識能力を高める効果が期待できるでしょう。
自己認識は自我の芽生えの第一歩で、自分と他人が違うことを理解します。
※参考文献:https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/539
多様な経験で感性を育てる
散歩時に目に触れる花やものなどについて語りかけると、脳によい刺激を与えます。さらに、以下のようなイベントに参加すると、日常では感じられない刺激を与えることができます。
インターネットや市報、商店街などのチラシなどをチェックすると、無料や低料金で楽しめるイベントがあるので、活用するとよいでしょう。
- オススメのイベント
・季節の行事(花見・海遊び・花火大会・紅葉狩り・クリスマスなど)
・音楽や絵画などアート体験
・イベントやアクティビティに参加する
・地域の親子教室や児童館イベント
・赤ちゃん向けコンサートやワークショップ
まとめ
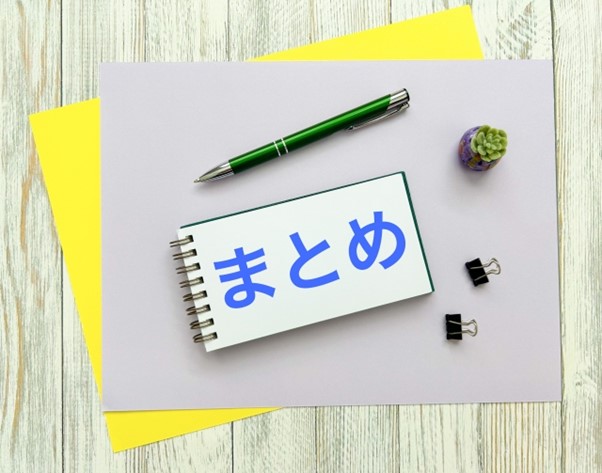
家庭でできる赤ちゃん教育は特別なことではなく日常の中にあり、少しの工夫や意識を高めることで、赤ちゃんによい刺激を与えることができます。
特に毎日の挨拶や絵本の読み聞かせは、すぐに実行できるためオススメです。継続のコツは「無理なく、楽しく」行うことです。
この記事を参考に日常生活に赤ちゃん教育を取り入れて、赤ちゃんの脳の発達をサポートしましょう。また、赤ちゃん教育についての他の記事はこちらにもあります。参考にしてください。


