赤ちゃんの発達は著しい!発達段階と家庭での関わり
サイト運営会社
株式会社城南進学研究社
「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん/アタマGYM」「りんご塾」 「Zoo-phonics Academy」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、 「城南進研グループ」を形成。

赤ちゃんの成長や発達には、個人差が大きくあります。そのため、他の赤ちゃんと比べて「我が子の発達や成長が遅いのではないか?」「何もしなくても大丈夫?」と焦りや不安を感じる親御さんは多いでしょう。
脳は5歳までに85%が完成すると言われているため、この時期にさまざまな刺激を与えることで脳の発達をサポートできます。しかし、赤ちゃんの教育は勉強だけではなく、「安心感」「遊び」「愛情」が、未来の学びに繋がります。
本記事では、「赤ちゃんの発達段階」を月齢ごとに整理しつつ、家庭でできる教育的な関わり方を解説します。
育児中の方やこれから育児が始まる予定の方、赤ちゃんの発達と関わり方に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
赤ちゃんの発達段階とは
 赤ちゃんの発達は、体・感覚・言葉・心の発達が相互に関連しつつ、総合的に進んでいきます。発達には個人差が大きくあるため、比べすぎないことが重要です。
赤ちゃんの発達は、体・感覚・言葉・心の発達が相互に関連しつつ、総合的に進んでいきます。発達には個人差が大きくあるため、比べすぎないことが重要です。
赤ちゃんの発達は、発達心理学や小児科の視点から見ても、「環境と親の関わり」が大きな影響を与えます。
他の子と比べて焦ってしまい、赤ちゃんに合っていない関わり方をしてしまうと、発達に悪影響を与えてしまう可能性があるため、注意が必要です。
この章では、赤ちゃんの発達段階を以下の5つに分けて、発達の特徴や教育的な関わり方を解説します。
・新生児期(生後0か月~2か月)
・生後3か月~5か月ごろ
・生後6か月~8か月ごろ
・生後9か月~12か月ごろ
・1歳~1歳半ごろ
新生児期(生後0か月~2か月)の発達と教育的関わり
●体の特徴
この時期の赤ちゃんは、視力は0.03~0.05で周囲がぼんやりと見えている程度です。首も座っていないため、抱く時には後頭部を支えないとグラグラします。
昼夜の区別なく寝て過ごし、不快な時は泣くことで表現します。2か月くらいになると、クーイング(喃語の前の段階で「あー」「うー」などの単語を発すること)が始まり、手足をさかんに動かすようになります。
●関わり方
この時期の赤ちゃんは、言葉を発したり理解したりできないため、コミュニケーションを取ることができません。しかし、抱っこやスキンシップ、マッサージ、声かけを行うと、赤ちゃんは愛されていることを実感し、安心感を覚えます。
「安心感」は、信頼関係の基盤となるため、大変重要な要素です。また、言葉を理解できなくても音やリズムを聞き分けることはできます。声かけは、赤ちゃんの脳に刺激を与え、言語習得や知能指数の発達を促すため、積極的に行いましょう。
生後3か月~5か月ごろの発達と関わり方
●体の特徴
この時期になると首が座り、昼夜の区別がつくようになってきます。首が座ることは、赤ちゃんの運動機能が成長するために重要です。
声を出して笑うようになり、喃語も出てくるでしょう。視力も0.04~0.08と高くなり、音や光にも反応するようになります。
また、赤ちゃんは、親の動作や口の形、声をまねすることで、自然にコミュニケーション方法を学んでいきます。
5か月くらいになると、寝返りをしたりうつぶせを長くできるようになったりする赤ちゃんも出てくるでしょう。
●関わり方
赤ちゃんに話しかける時は、目を見て話しましょう。赤ちゃんは、目を合わせて話しかけた人を覚えていることが研究の結果判明しています。※参考
また、歌いかけも、安心感を与えたり、言語習得をサポートしたりする効果があり、これらのやりとりが、言葉や社会性の基盤となります。
赤ちゃんとスキンシップやコミュニケーションを楽しむ「触れ合い遊び」は、安心感や感覚機能の成長、記憶力や思考力のサポートなどの効果があるため、おすすめです。
触れ合い遊びには、「いっぽんばしこちょこちょ」「むすんでひらいて」などの歌に合わせて動きを楽しむものや、いないいないばあ、マッサージ、赤ちゃん体操などさまざまなものがあります。インターネットで検索するとたくさん紹介されているため、参考にするとよいでしょう。
生後6か月~8か月ごろの発達と関わり方
●体の特徴
お座りができるようになり、多くの赤ちゃんが寝返りをするようになりますが、9か月ごろにする場合や寝返りをしないで次のステップにいく場合もあります。
歯が生え始める赤ちゃんもおり、6か月ごろになると離乳食が始まります。また、「アーアー」「ブーブー」など、声を出して発声練習をするようになるでしょう。
●関わり方
この時期の赤ちゃんの脳は、視覚 、 聴覚 、 触覚 、 味覚 、 嗅覚の五感からの刺激をダイレクトに受け入れます。絵本の読み聞かせは、絵を見ることで視覚を刺激し、言葉のリズムを楽しむことで聴覚を刺激するため、積極的に取り入れるとよいでしょう。
色々な素材でできたおもちゃを触ると触覚に刺激を与え、さまざまな食材を体験すると嗅覚や味覚に刺激を与えます。五感を刺激することを、日常生活の中で意識するとよいでしょう。
生後9か月~12か月ごろの発達と関わり方
●体の特徴
9か月になるとハイハイが上達し、11か月ごろにはつかまり立ちや伝い歩きが活発になります。言葉のような発音ができるようになり、大人の言葉を理解できるようになります。
ママの後追いをしたり人見知りをするようになったりするのもこの頃からです。12か月になるころには早い子は歩き出し、夜まとまって寝るようになります。前歯が生えそろい、1日に3食+おやつを食べるようになります。
●関わり方
行動範囲がどんどん広がるため、安全な環境を整えることが大切です。好奇心も活発になるため、安全な散歩道や公園などの環境を用意して、「やってみたい」を尊重しましょう。
やってみた結果がうまくいかなくても、叱ったり否定したりしないことが重要です。試行錯誤の体験が「考える力」の芽になります。
1歳~1歳半ごろの発達と関わり方
●体の特徴
1歳を過ぎると、運動や言葉の能力が急激に発達し、赤ちゃんから子どもへと変わってきます。ほとんどの子どもが安定して立つことができるようになり、歩き出す子どもも増えます。
言葉の理解度も進み、「まんま(ご飯)」「ブーブー(車)」など意味のある言葉を発することができる子どももいるでしょう。
この時期は発する言葉と理解できる言葉の数に大きな差があり、話す言葉の数より理解できる言葉の数が大きく上回っているのが特徴です。日頃から、できるだけ多く話しかけるよう心がけるとよいでしょう。自立心が芽生えるのもこの時期からで、自己主張も激しくなります。
●関わり方
行動範囲が広くなりできることがずっと増えてきますが、危なっかしいため、親はついつい手や口を出しがちです。しかし、先回りして子どもに考えさせたり選択させたりする機会を与えないでいると、自立心や創造力が育ちません。
安全には注意を払いつつ、子どもの「自分でやりたい」を応援しましょう。自立と挑戦を大切にすることで忍耐や自己効力感(自分ならできると認識・確認すること)などの非認知能力が育ちます。
赤ちゃんの発達を見守る時の注意点
 最後に、赤ちゃんの発達を見守る時の注意点を2点、解説します。注意点に気をつけつつ、赤ちゃんの成長を楽しみましょう。
最後に、赤ちゃんの発達を見守る時の注意点を2点、解説します。注意点に気をつけつつ、赤ちゃんの成長を楽しみましょう。
・比べすぎないこと
・気になるようなら専門機関に相談する
比べすぎないこと
この記事の中でも述べてきましたが、赤ちゃんの発達には個人差が大きくあります。インターネットの記事や本などの情報を見たり、周囲の年齢が近い赤ちゃんと遊んだりすると、ついつい比べてしまう方も多いでしょう。
しかし、「うちの子の発達、遅いのでは?」「何もしなくても大丈夫なのか?」などと考えてイライラ、ハラハラしたり、「もっと!」とせかしたりしてしまうと、赤ちゃんとの信頼関係が育ちにくくなり、赤ちゃんの情緒の発達にも悪影響を与えてしまいます。
「そのうち追いつくだろう」「マイペースでいこう」とゆったりと構えて、毎日を笑顔で過ごすことが大切です。焦っても、教育的にも精神的にもプラスにはなりません。
気になるようなら専門機関に相談する
子どもの発達については、親はゆったりと構えることが重要ですが、中にはなんらかの発達障害がある場合もあります。
発達障害がある場合は、親や周囲の理解や正しい対応が重要です。発達障害が原因なのに、周囲から親の育て方が原因のように思われると、親のストレスが増し、親も子どもも追い詰められることがあります。
どうしても気になる場合は、以下の専門機関に相談するとよいでしょう。
・小児科や専門の医療機関
・市町村の保健所や保健センター
・発達障害者支援センター
・児童発達支援センター
・児童相談所
インターネットで専門の医師が質問に答えてくれるサイトもあるため、出かけるのが困難な場合やすぐに相談したい場合は、面談での相談と併用するとよいでしょう。
まとめ
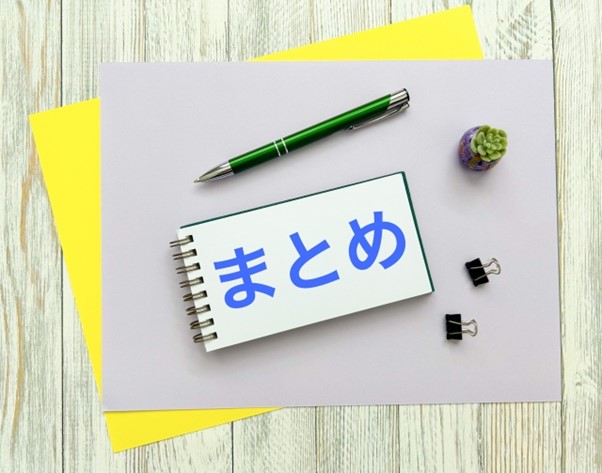 赤ちゃんの発達は急激なため、発達段階をしっかりと理解することが、「教育の第1歩」です。
赤ちゃんの発達は急激なため、発達段階をしっかりと理解することが、「教育の第1歩」です。
赤ちゃんの発達には、親の愛情ある関わりが重要なポイントで、赤ちゃんの未来の学びや人間性の土台になります。
しかし、発達段階にこだわりすぎると、笑顔で子どもの成長を見守ることができなくなり、親にとっても赤ちゃんにとってもマイナスになることはあってもプラスにはなりません。
焦らずに、赤ちゃんと一緒に楽しむ気持ちを大切にして、成長を見守りましょう。
ご紹介
「忙しくても大丈夫!家庭でできる赤ちゃん教育の具体的な方法を徹底解説」も併せて、ご覧ください。詳しくは、こちらから


