幼児教育の環境づくり完全ガイド|家庭でできる工夫とポイント
サイト運営会社
株式会社城南進学研究社
「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん/アタマGYM」「りんご塾」 「Zoo-phonics Academy」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、 「城南進研グループ」を形成。

人間の脳は5歳までに85%が完成するため、幼児教育を行い脳に刺激を与えると、脳の発達をサポートできます。
ただし、この時期は発達が著しい上に、発達段階に個人差があります。そのため、環境を整えて子どもに合った教育を行わないと、期待する効果が得られない可能性があります。
この記事では、幼児教育に必要な環境の作り方やポイントを、具体例を紹介しながら詳しく解説します。
育児中の方やこれから育児が始まる方、幼児教育における環境作りに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
1.幼児教育に必要な環境とは?

幼児教育に必要な環境は、以下の3つです。
- 安全な遊び場
- 創造力を刺激する環境
- 発達段階に合わせた支援
1-1. 安全な遊び場
幼児教育を行うためには、まずは子どもが安心して学べる安全な環境を整えることが重要です。
以下の3つのポイントを押さえて安全な環境を整えましょう。
1‐1‐1.子どもが自由に遊べるスペースの確保
子どもが自由に遊べるスペースには、自宅の部屋や庭、公園、公共の施設などが挙げられます。
幼児教育は、毎日子どもの負担なく続けることが重要なため、自宅を中心に日常的に利用しやすい場所を選びましょう。
公園や公共の施設の場所がわからない時は、ママ友に尋ねる、インターネットで検索する、お住まいの市町村の役所や役場に問い合わせる、などの方法で調べることができます。
1‐1‐2.遊び場の安全性チェックと事故防止対策の具体例
室内は、家具をできるだけ壁際に移動して、身体を動かすスペースを作ります。
事故防止対策として、以下のことが挙げられます。どれも難しいことではないため、積極的に取り入れましょう。
- 室内対策
・角のない家具を選んだり保護材を貼ったりする
・転倒防止のグッズを使用して家具が倒れないようにする
・床にはクッション性のある素材を使用したり、床の上に敷いたりする
・階段やベランダには柵をつけて侵入できないようにする
・ブラインドやカーテンなどのひも類は、お子様が誤って首に絡ませて窒息する危険性があるため、手が届かないようにする
・誤飲を防ぐため、はさみ、ボタン電池、包装フィルムやシール、化粧品、医薬品、たばこ、酒などを置きっぱなしにしないようにする
- 公園などにおける対策
・突起がないか、ボルトのゆるみがないかを確認する。
・つまずきの原因となる石や障害物があれば取り除く
・大人の目線ではなく子どもの目線で確認する
1‐1‐3.さまざまな遊具や教材の活用
幼児教育は、高価な教材を使わなくても行うことができます。
公園や遊び場にある遊具を使って遊ぶと、走る、登る、滑る、バランスを取る、這うなど、身体能力を高めることができます。
砂場は、触覚を刺激する、スコップやバケツなどの道具を使う、足場の悪いところで歩く、しゃがむ、などの動作をするため、手先の巧緻性やバランスを取る、体幹の強化など、多くの効果が期待できます。
また、絵本の読み聞かせは、言語習得や創造力、知能の発達を促します。図書館を利用すると、家計に負担をかけずに多くの絵本に触れることができるため、おすすめです。
1‐1‐4.地域の保育施設や情報サイトを利用する
地域の保育施設では、さまざまなイベントやプログラムが用意されていることが多くあります。
異年齢の子どもや普段接することがない大人と接することができるため、コミュニケーション能力や価値観の学習に役立ちます。
以下を利用すると、参加できるイベントやプログラムを見つけることができるでしょう。
・住んでいる地域のホームページ
・幼稚園、小学校、商店街の掲示板、
・公共施設の案内所、
・インターネットの情報サイト
2.創造力を刺激する環境作りが必要

創造力とは新しいものを自分で生み出す力で、子どもがこれから社会で生きていく上で必要な力です。
創造力は、以下の方法で刺激することができます。
- 多様な素材や道具で創造性を引き出す
- アート、音楽、実験など体験型学びの機会を提供する
- 自由に考え、表現できる環境を整備する
2‐1.多様な素材や道具で創造性を引き出す
創造力は、子どもが自由に遊ぶことで引き出すことができます。決まった使い方をする道具ではなく、自由に使うことができるものを用意するとよいでしょう。
具体的には、積み木やブロック、粘土、紙、空き箱、ラップ類の芯、折り紙、はさみやのりなどの工作グッズなどが挙げられます。
また、絵本も創造性を引き出す教材の1つです。
2‐2.アート、音楽、実験など体験型学びの機会を提供する
体験型の学びは、実践力や応用力、考える力、社会性、問題解決能力の育成、基礎体力や心身の健康の保持、など、高い教育効果が期待できます。
どれも身近にあるもので安価で用意できます。
- 絵を描く・・・紙、クレヨンを用意する
- 音楽を聴く・・・CDやインターネットを利用する
- 楽器を演奏する・・・家庭にある楽器や子どもが興味を示した楽器を用意する(できる範囲で)
- 家庭でできる実験・・・絵が浮き出るトーストやスライム作りなど。インターネットで検索すると多く紹介されているので利用するとよい
3.発達段階に合わせた支援が必要

幼児教育で期待する効果を得るためには、年齢や発達段階に合わせた支援を行うことも重要なポイントです。
子どもの発達は著しいため、年齢や発達段階に合わない教育を行うと、十分な効果が得られなかったり、逆効果になったりする可能性があります。
この章では、発達段階に合わせた関わり方を詳しく解説します。
3‐1.子どもの年齢・発達段階に応じた関わり方
子どもの発達段階は、月齢別、年齢別、などさまざまな段階で分けることができます。ここでは、発達段階を乳児期、幼児前期、幼児後期の3つに分けて発達の目安や関わり方を解説します。
ここで紹介するのは、あくまで発達の目安です。子どもの発達には個人差が大きくあるため、目安通りにできなくても神経質にならないようにしてください。
親の不安やイライラは子どもに伝わり、発達を妨げる可能性があります。どうしても不安に思う場合は、かかりつけの小児科や市町村の保健所、保健センターなどに問い合わせるとよいでしょう。
- 0~1歳半(乳児期)
身体的な発達が最も著しい時期で、寝返り→お座り→はいはい→つかまり立ち→歩行と、発達します。
また、言語や情緒の発達も著しく、1歳になるころには簡単な言葉を理解し、人見知りや後追いなどの行動も見られます。
この時期の赤ちゃんは、言葉でコミュニケーションを取ることは難しいため、スキンシップが特に重要です。
また、話しかけや歌を歌うなどで言語の発達を促すように心がけるとよいでしょう。
- 1歳半~3歳(幼児前期)
一人で歩くことができるようになり、行動範囲が飛躍的に増えます。自我が芽生えはじめ、やりたい、やりたくない、などの自己主張が始まり、自立心が芽生えはじめます。
自立心は、子どもがこの先の人生を歩んでいく上で重要な要素です。子どもの意思をできるだけ尊重し、危険が伴わないことは、手や口を出さずに見守るように心がけましょう。
また、言葉能力も高まり、コミュニケーションが取れるようになって、理解力や表現力も高まってきます。
親子で会話する機会を増やすことを心がけたり、乳児期に引き続き絵本の読み聞かせを続けたりしましょう。
- 3~6歳(幼児後期)
ルールを理解できるようになり、社会性も高まります。協調性も身に付き、集団で遊ぶことができるようになります。創造力も豊かになるため、ごっこ遊びや創作活動を楽しむようになるでしょう。
この時期は、なぜなぜ期とも呼ばれ、子どもの好奇心が強くなる時期です。子どもが「なぜ?」と聞いてきたら、理解できるように丁寧に答えたり、一緒に疑問を解決したりして、好奇心を尊重することが重要です。
好奇心が育まれると、「もっと知りたい!」という気持ちが芽生え、学習意欲が高まります。
3‐2.特に3歳前後の基礎的教育は重要
子どもの成長は著しいですが、特に3歳前後は、身体的、精神的にめざましく成長するため、この時期に基礎的な教育を行う必要があります。
この時期に育まれる自我の形成は、自分と他者との違いを認識して折り合うことを覚え、社会性の発達へと繋がります。
また、3歳前後は、知能や理解力、思考力、記憶力などの認知能力が発達し、知的好奇心も高まります。上記で解説したように、子どもの「なぜ?」には、丁寧にわかりやすく対応しましょう。
これらの要素は、子どもがこれからの長い人生をよりよく歩いていくために、重要です。焦らず、ゆっくりときめ細やかな対応を心がけることが大切です。
3‐3.1人ひとりに合った対応をする
子どもは1人ひとり、発達スピードが異なります。また、性格に合う対応も必要なため、「〇歳になったらこれができなければならない」という基準はありません。
特に、兄弟がいる場合は、下の子に対して上の子の時と同じ対応をしがちですが、それぞれ、得意なこと、苦手なことが異なります。
「お兄ちゃんはできたのに」「弟の方が上手にできる」など、兄弟と比べた発言は、「自分はダメな子だ」「兄弟の方が愛されている」と感じ、自己肯定感を低くしたり、無気力感、嫉妬心を持ったりし、最悪の場合、うつや不安などの症状が出やすくなることもあります。
兄弟を比較することなく、1人ひとりの性格や成長のスピードに合わせて、丁寧な対応をするよう心がけましょう。
4.まとめ
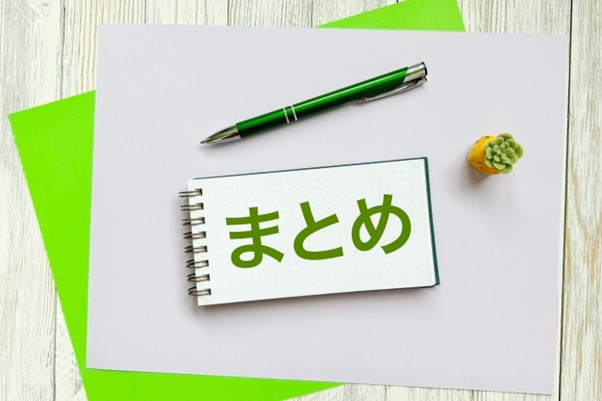
幼児教育における環境整備のポイントは、安全、創造力、発達段階に合わせた支援の3つです。この3つの教育環境が欠けることなく整うと、子どもがより豊かに学び、成長することができます。
特に安全な環境を整えることは、子どもの健康や生命を守るためにも安心してさまざまな学びに取り組むためにも、重要です。
安全な教育環境を整えた上で創造力の育成や発達段階に合わせた支援を行うと、期待する教育効果を得ることができるでしょう。
この記事を参考に教育環境を整え、子どもの未来をよりよいものへと導きましょう。


